「意志ある成長」を実現する組織づくりに向けて、FFS理論を導入 ~全社員にワークショップを実施し、マネジメントやキャリア構築にも活用

お話を伺った方:須山 一成 様(執行役員CHRO HR本部長)
.ai_-480x270.png)
会社名:レジル株式会社
業種:電力
従業員数:260名(2025年6月)
- 導入範囲:全社導入
- 導入時期:2024年~
- 課題
-
- 人材マネジメントの方向性・コンセプトは設定できていても、具体的な実践ができていなかった。
- 上意下達型のマネジメントになっており、心理的安全性の低下、ハラスメント・メンタル不調、「言われたことしかやらない組織」になる等のリスクがあった。
- 効果
-
- 相互理解ワークショップを通して社員それぞれが個性を理解し、自身の成長のためにとるべき具体的な行動を考えられるようになった。また、人材マネジメントにおける方法論が実装できた。
- 上司が部下の個性にあわせたマネジメントができるようになり、部下も「言われたことだけやる部下」から「自分の意志・強みをどう出すか考える部下」へと意識改革が進んだ。
【課題意識】
「意志ある成長」を具体的に進めるための”武器”が必要だった
―須山さんはどういった形で今の会社に参画されたのでしょうか
須山さん 私が入社したのは約2年前で、当時は会社として上場を控えているタイミングでした。HR担当の役員を探していたとのことで、縁あって、その任を担うことになりました。
―会社にとっては変革のタイミングだったわけですね
須山さん 当社はエネルギー事業に取り組んでいるのですが、もともとは分譲マンション向けの「一括受電」を主力事業として発展してきました。マンションに居住されている全世帯と電力契約を結び、各戸に電力を供給するというサービスです。しかし2016年の電力自由化によってこの領域の競争が激化し、事業ポートフォリオを見直す必要が出てきました。そういったマーケット変化を受けて、2019年に社長就任したのが、現社長の丹治です。会社として「脱炭素」という大きなビジョンを掲げ、分散型エネルギー事業、グリーンエネルギー事業、そしてエネルギーDX事業という三本柱で新たな事業戦略を打ち出しました。
―組織としては、どのような変化が求められたのでしょう
須山さん 一括受電の事業においては、やるべきことを粘り強くやることが強く求められます。たとえばマンションの住人100人のうち99人がサービス導入に同意いただいても、残り1人に同意をいただけないとサービス提供がスタートしません。そのため粘り強くアプローチをする必要があり、社内には「とにかくやるぞ!」という行動ドリブンな文化が根付きました。しかし、事業環境に変化があり、一括受電を主軸としたビジネスモデルからの転換が必要となりました。そのため、これまでの戦略にとって最適だった組織文化を、これからの戦略にとっての最適に変革させる必要がありました。
―その変化をどう実現しようと考えたのでしょうか
須山さん 事業戦略と人事戦略の間をつなぐ、人材マネジメントのキーワードとして「意志ある成長」というコンセプトを置きました。脱炭素はまだ誰も達成したことがないから、誰かに答えを聞いて実行するようなものではありません。自ら問いを立て、答えを創れる人材が必要です。だからこそ、このコンセプトを上位に据え、それを落とし込む人事戦略、そして施策という順番で考えました。
―それが人事制度の変革につながるのですか?
須山さん 大きな制度改定自体は、実は私の入社前に進んでいました。「働き方が変わらなければビジネスモデルは変わらない」という考えのもと、まずは環境面を整えたのです。たとえば、スーパーフレックス、服装の自由化、副業の推奨、書籍購入補助など、いわばモダンなスタートアップの標準装備を一通りそろえました。
私の役割は、その“働きやすさ”を土台にして、その先にある「意志ある成長」をどう具現化させるかに焦点を移し、具体的な施策へと落とし込むことにしました。
【導入の経緯】
働きやすさの土台が整ったタイミングで導入
―その流れから、FFS理論の導入に至ったということでしょうか
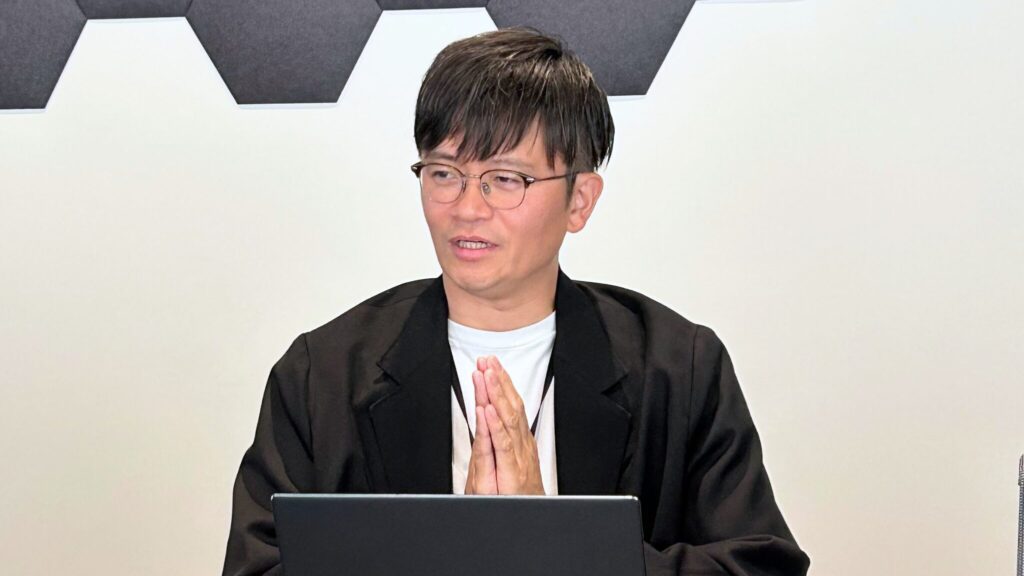
須山さん そうですね。従来の組織運営は実行力に重心があり、「やるべきことを愚直にやり切る」という上意下達型のマネジメントでした。そこから一転して、「あなたはどうしたいのか」と個人の意志を問うスタイルへ切り替えるのは大きな変化です。
「意志ある成長」という概念だけを掲げても実効性は高まりません。現場で使える“武器”が要ると考え、前職で活用していた FFS理論 を思い出しました。意志を持つには、自分の強みや“らしさ”の理解が不可欠です。その共通言語としてFFSは有効だと判断し、導入を決めました。
―他のツールも検討されましたか?
須山さん 自己理解を深めるツールはいくつもありますが、理論だけでなく、運用面まで伴走してくれる仕組みが整っているのはFFS理論だけでした。 また、多くの会社で導入されているサーベイは結果が折れ線グラフで表示され、個性を直感的にとらえるのが難しい印象がありました。その点FFSは、アルファベット5つの組み合わせで個性を表すシンプルな設計になっており、誰にでもわかりやすく理解しやすいのが特長です。さらに、個人の自己理解にとどまらず、マネジメントやチーム編成といった組織運営にも応用できる汎用性がある。こうした総合的な観点から選びました。
―導入のタイミングはどのようにお考えでしたか?
須山さん 当社では先に働きやすさの施策を整えていたこともあり、FFS導入の受け止めは非常にスムーズでした。導入時には「自分の個性がこう表れるのは少し違うかも」という声もありましたが、全体として否定的な反応はほとんどありませんでした。
もしこの基盤づくりを経ずに導入していたら、「その前にやるべきことがあるのでは」と受け止められていたかもしれません。FFSのようなツールは、働く環境や制度がある程度整い、次のステップとして人の成長に焦点を移す段階でこそ、最も力を発揮すると感じています。
―最初は経営層のワークショップを行ったそうですが、その時の反応はいかがでしたか
須山さん 概ね想定どおりの反応でした。「自分の個性は少し違うかもしれない」と話す人もいましたが、多くの方は「たしかにそうだよね」と納得されていました。全社展開への抵抗感もほとんどなく、「いったんやってみよう」という前向きな声が多かったですね。特に、組織運営に課題を感じていた経営陣ほど、「自分の本部でまず試してみたい」と関心を示してくれたのが印象的でした。
【浸透の工夫と効果】
全社員へのワークショップ実施は、会社の姿勢を伝えることにもなる
―全社展開をする際には、どのような工夫をされましたか?

須山さん 一時は解説動画の視聴で済ませる案もありましたが、やはり対面でしっかりと実施する方が学習効果は高いと判断しました。加えて、ワークショップ形式であれば、互いに意見を交わしながら自分の個性や他者の特性を体感的に理解できる点も大きな利点です。さらに、会社としてこのテーマに本気で向き合っている姿勢を示すことにもつながります。「意志ある成長」を掲げる以上、それをお題目で終わらせず、全社員が考え、対話し、実践する場を設けること自体が強いメッセージになる。そうした意図を込めて、全員参加の対面ワークショップを実施しました。
―ワークショップは全員必須でしょうか
須山さん はい。日程枠を一斉に展開して、参加できるところに名前を入れてもらいました。ただしメンバー層とマネジャー層は分けています。メンバー層は自己理解を中心にした内容、マネジャー層は自己理解+マネジメントへの活用という内容にしました。マネジャーには各々のチームメンバーの個性も具体的に見てもらっています。
―relateとしてワークショップを担当させてもらいましたが、外部リソースの活用は最初から考えていたのでしょうか
須山さん 当社でFFS理論の資格をとっているのは私ともう1人だけで、お互いこのワークショップばかりに時間はかけられません。スピード感を出すには外部の力を借りようと、最初から考えていました。もともと人的資本投資をきちんとしていこうという会社の姿勢もあり、ある程度の予算は確保していました。全社員向けワークショップは短期間でやりきる方が良いと思ったので、relateさんには短期集中で多くの支援をいただきました。
―皆さんがFFS理論を知ったことで、何か変化等が起こっていますか?
須山さん 特にマネジャー層から、「こう関わればよいのか」「すれ違いの理由が分かった」という気づきの声を多く聞きました。今までは相互理解のための時間はとっていたものの、お互い何となく察しながらという雰囲気でした。個性がわかると踏み込み方がわかるので、関わり方ももう少し建設的になる気がしています。
―同意を得た人は因子を社内公開しているとか
須山さん はい。本人の公開同意が取れている場合に限りますが、おおよそ9割程度は、Notion上で公開しています。実際に社内では、「あの人、どんな因子だったかな?」と確認している様子を見かけることもあり、そこそこ見ているかもしれません。
―関係性の変化が効果をもたらしたような経験はお持ちですか?
須山さん 前職でマネジャーをしていたときの話ですが、自組織内のリーダーと新人の関係がうまくいっていない時期がありました。リーダーは「まずは自分で考えて、自由にやっていいよ」と言い、新人は「まずはやり方を教えてください」と求めるといった、典型的なすれ違いです。FFSで見ると、リーダーは拡散性が高いタイプ、新人は保全性が高いタイプという真逆の組み合わせでした。リーダーは「なぜ動かないんだ」と苛立ち、新人は「なぜ放っておかれるんだ」と不安を感じていたのです。 しかし、FFS理論を学んだ後、リーダーが「依然として動かないのは変わらないけど、なぜそうなるのか理由がわかったから、納得できた。」と口にしていました。お互いの行動の背景を理解できたことで、感情的な対立が和らぎ、違いを踏まえて関わり方を変えようとする建設的なアクションが生まれるようになりました。
―お互いの行動原理が分かったというのは大きいですね。
須山さん そうなんです。感情と感情の間に入る“クッション”のような役割を、FFSが果たしてくれたと感じています。お互いの特性を理解できると、「この人にこう言っても響かないんだな」「こう伝えた方が伝わりやすいんだな」といった関わり方の違いに気づけるようになる。そのちょっとした気づきが、衝突を和らげ、コミュニケーションを前向きに変えていくのだと思います。
【今後の展望】
組織づくりは10年の計。焦らず根付かせる
―今時点の効果としては、どのように見ていらっしゃいますか。

須山さん 今は、まず「何のためにFFSを導入したのか」という考え方を丁寧に伝える段階だと考えています。
そのため、一気に推進して“流行らせる”ような動きはとっていません。流行は広まるのも早いですが、廃れるのも早い。だからこそ、長期的に根付かせることを念頭に、現実的なスピードと丁寧さを大切に進めています。
特に重視しているのは「有用感」です。無理に押し込むのではなく、「これは使えそうだ」「自分の仕事に役立つ」と実感してもらうこと。その小さな体感の積み重ねこそが、文化として定着する近道だと思っています。
実際、各種ワークショップやイベントでも有用感のスコアが高く、現時点では順調に浸透していると感じています。
また、「意志ある成長」に関するサーベイ結果でもスコアが昨年より上昇しており、FFSの取り組みが良い影響を与えていると感じます。
―全社員ワークショップの次には、いくつか別テーマでワークショップを実施されているそうですね
須山さん 新人マネジャー向けワークショップ、相互理解ワークショップ、1on1キャリアセッション、キャリアデザイン講座というものを、今、進めています。どれもまずは小規模での開催ですが、網羅的にラインナップを持っておきたいというのが私の意図です。困ったときに「こういうのがあるよ」と提示できる状態にしたいと思っています。
―今後の展望はどのような感じでしょうか
須山さん 組織づくりは十年の計と捉え、拙速を避けて着実に進めていきたいと考えています。「意志ある成長」を中心に据え、FFSの「個性を活かす」という考え方を梃子に、自己理解・相互理解・メンバー理解を深めていきます。 実務の中で有用感を積み重ねながら、長期的に文化として定着させていきます。