“なんちゃって転職”の罠。市場価値を失わないためのキャリア形成
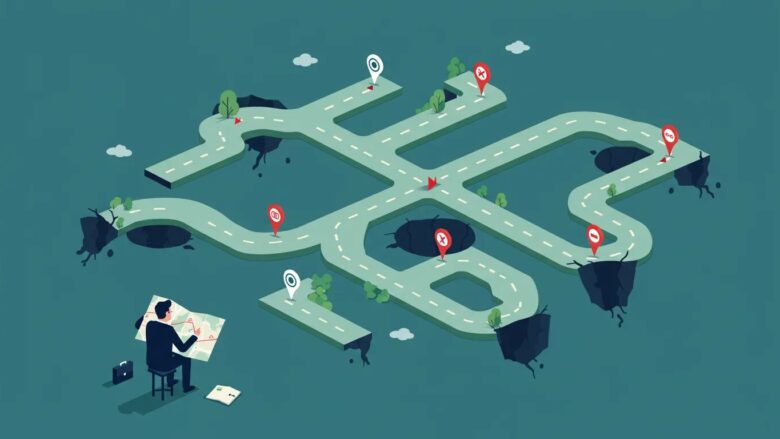
こんにちは、relate株式会社ファウンダーの吾妻聡平です。
「キャリアアップのために転職を考えている」
「より良い環境で自分の力を試したい」
キャリアに対する意識が高まる中、転職は当たり前の選択肢となりました。しかし、その一方で、明確な実力の裏付けがないまま給与だけが上がっていく「なんちゃって転職」に陥り、気づかぬうちに自らの市場価値を毀損している人が増えているという、深刻な現実があります。
今回の記事では、多くの人が陥りがちなキャリア形成の罠に警鐘を鳴らします。なぜ貴重な時間が「積み上がらないキャリア」として浪費されてしまうのか。そして、偶発性に流されるのではなく、10年後、20年後も社会で輝き続けるための「戦略的キャリア設計」とは何か、その本質に迫ります。
1.あなたのキャリアは積み上がっているか?「1万時間」の法則と“なんちゃって転職”の末路
一つの分野の専門家になるには「1万時間」が必要と言われます。キャリアとは、こうした専門性を複数掛け合わせることで、市場価値を高めていく営みです。しかし、この「1万時間」が全く積み上がらないまま職を転々としてしまう人が後を絶ちません。
特に近年は、好条件での転職が可能な市場環境も手伝い、「何も身につけていないのに、転職によって給与だけが上がっていく」という危険な現象が起きています。これが「なんちゃって転職」の正体です。一見すると成功しているように見えますが、その実態は、年齢と給与だけが上がり、スキルと経験が全く追いついていないという“キャリアの空洞化”です。その先に待っているのは、40代になって「自分には何の専門性もない」と気づく残酷な現実かもしれません。
「悪いキャリアの歩み方」とは、まさにこのような「自己理解なく、何の積み上げもないまま場当たり的にキャリアを歩んでしまうこと」に他なりません。自分の時間をどこに投下し、何を積み上げるのか。その視点が無いキャリア選択は、時間を浪費するだけでなく、未来の可能性そのものを失う行為なのです。
2.すべては最初の出会いから。キャリアの成否を分ける「最初の上司」という最重要ファクター
では、キャリアを豊かにする「良い経験」や、成長の糧となる「深い気づき」は、どこから生まれるのでしょうか。それは突き詰めると、「上司との関係性」に集約されます。キャリア形成において、ファーストキャリアで「誰を上司に持つか」は、その後の社会人人生の羅針盤となるほど重要なのです。
しかし、多くの企業では、この初期配属において、場当たり的なアサインが横行しているのが実態です。会社側が「最初の上司が、その新人の人生を大きく変える」というほどの真剣さで配属を考えていない。この判断ミスが、個人のポテンシャルを潰し、早期離職を招くだけでなく、日本社会全体にとっての大きな損失(ソーシャルロス)を生み出していると私は考えています。
本人とマッチする「良い上司」との出会いは、個人の成長を加速させる最高の触媒となります。それは、部下の個性を理解し、適切なフィードバックを与え、時にはストレッチの効いた挑戦の機会を与えてくれる存在です。キャリアを歩む個人側も、1社目がどこかという会社選びだけでなく、「誰の下で働き、何を学ぶか」という視点を持つことが、最初の1万時間を価値あるものにするための鍵となります。
3.キャリアの本質は“誰と働くか”にある
キャリアの話になると、多くの人が「次にどんなスキルを身につけるべきか」という議論に終始しがちです。もちろんスキルは重要ですが、それだけでは本質を見誤ります。なぜなら、仕事は常に他者との協働であり、良い経験から良いスキルを学べるかどうかは、すべて人との出会いや関係性にかかっているからです。離職理由のほとんどが人間関係であることからも、その重要性は明らかでしょう。
良い出会いを質の高い学びに変えるために、土台として不可欠なのが「自己理解」です。自分がどのような人間で、何に価値を感じ、どういう状況で力を発揮できるのかを深く知ること。これが、キャリアの羅針盤を手に入れる第一歩です。
自己理解ができて初めて、他者との関係性の中で学びを最大化し、自分に合った「良い経験」とは何かを見極めることができます。スキルという“点”でキャリアを捉えるのではなく、自己理解をベースに、関係性の中でどのような経験を積んでいくかという“線”でキャリアを設計していく。この視点こそが、これからの時代に求められるキャリア形成なのです。
4.個人と会社が共創するキャリア。これからの企業に求められる責任とは
企業が「社員一人ひとりのキャリアに真剣に向き合うこと」は、単なる福利厚生ではなく、企業の競争優位を左右する重要な議題となります。一部の先進的な企業では、個人のキャリアプランを考慮した採用やアサインが実践されていますが、残念ながら日本の多くの企業では、社員のキャリアについて面と向かって対話する文化を定着できないでいます。
企業は、社員の個性とポテンシャルを正しく「見立て」、成長につながる機会を提供していく責任があります。そして私たち個人も、会社にキャリアを委ねるのではなく、自らの個性を深く理解し、主体的にキャリアを設計していく姿勢が求められています。「自分のキャリアについて、会社がここまで考えてくれている」。そう感じられる企業に、優秀な人材が集まるのは必然と言えるでしょう。
5.まとめ:キャリアは“与えられるもの”から“自ら築き、勝ち取るもの”へ
- キャリアの積み上げなき「なんちゃって転職」は、長期的に見て市場価値を毀損する大きなリスクとなる。
- キャリア初期の成長は「誰を上司に持つか」で大きく変わる。キャリア形成に「関係性」の視点を取り入れることが必要。
- スキル偏重のキャリア論から脱却し、「自己理解」を土台に関係性の中で経験を積むという視点を持つことが不可欠。
- これからの企業は、社員のキャリア形成を支援することが競争優位性につながる。
もしあなたがご自身のキャリアに迷いを感じているなら、それは才能の問題ではなく、キャリア設計の方法論を知る機会がなかっただけかもしれません。自分自身の個性を深く見つめ直すことから、後悔しないための戦略的なキャリア設計を始めてみませんか。
◆お問い合わせ
「自分の個性を活かしたキャリアプランを考えたい」「社員のキャリア開発を支援し、定着率とエンゲージメントを高めたい」といった課題をお持ちの経営者・人事責任者の方は、ぜひrelate株式会社にご相談ください。FFS理論に基づき、一人ひとりが輝くキャリア設計と組織作りを支援します。
お問い合わせはこちらのフォームよりお願いいたします。
https://relate-inc.co.jp/inquiry/